第8話:『レコードエンジニアさんの仕事って「プロの領域」だ!!』
ボーカル収録後のトラックダウン作業が始まりました。
音楽プロデューサーの藤田さんが、たくさん歌ったトラックのなかから意図に沿った歌い方をしたトラックを選びます。
そのボーカルの本線トラックデータを中心に、別のトラックのある歌詞部分のボーカルがより良ければそれと本線のボーカルのデータを入れ替えます。
アニメ的に言うと、編集します。
さらに気になる箇所を細かく収録したデータをつないで行きます。
レコーディングエンジニアさんがまとめたボーカルを藤田さんが最終確認して決定すると、次は、ボーカルと楽器の調整となります。
そして、2チャンネル(左右、ステレオ)にするためのミキシング作業が続きます。
ボーカルの音量、音場。それぞれの楽器の音量、音場など調整して行きます。
ちなみに、各楽器の音源は、シンセサイザーと生楽器で作られています。
わたしが見たなかで、ギターはボーカルの後に収録することが多いなって思いました。多分理由があると思いますが、その理由を聞かずじまいです。あ~、当時聞けば良かったです。
ある作品のとき、ギターの演奏家さんがこの歌は何に使うの?と質問を受けたときに、わたしはアニメの主題歌なんです、と答えましたら「子供が聴くのか?そうか、尚更に良い曲にしないとな、力を入れて弾くぞ!」と、子供が聴いてくれると知ると俄然テンションアップして演奏をしてくれた方がいました。とても、嬉しかったです。
さて、1時間、2時間とエンジニアさんの作業が続いて、とあるタイミングでその段階の歌をDAT(当時、デジタルで録音・再生の小型のデッキ)に録音して、外に出ていくのです。最初は、何をやっているのかが分からず、藤田さんに質問しました。
あれは、外の雑踏のなか、雑音のなかで歌をヘッドホン(イヤホン)で聞くためにやっていることだと教えてもらいました。
スタジオのなかは、凄い良い音で聞ける環境です。雑音はありません。街行く人もいません。
でも、エンドユーザーは、電車のなかで聞くかも知れません。道路を歩きながら聞くかも知れません。また、車のなかで聞くかも知れませんし、受験勉強しながら自分の部屋で聞くこともあるでしょう。さらに、スタジオ内にあるラジカセでも、音を出して聞いていました。
音は、環境(電車内、外の道路、車のなか、部屋のなかなど)によって、反響したり、こもったり、低音が聞こえにくかったりします。
また機材(ヘッドホン、イヤホン、ラジカセ、ステレオ、映画館のスピーカーなど、)によって出やすい、あるいは出にくい、聴こえにくい周波数帯があります。
さらに環境によって、高域が減衰したり、低域が出にくくなったりします。
何故か?と言うと、音は空気が震えることで聴こえるのです。遠くになると聴こえにくいし、遮蔽物などがあると音は聞こえにくくなるし、スポンジなどがあると音を吸い込みます。
大きな劇場では、人が入る前と、全員が椅子に座る後では音の音量が変わります。つまり、人間が音を吸い込むようでして、音量が減衰すると聞きました。
だからこそ、その環境によって音の伝わり方が大きく変わるのです。
さて、音って何でしょう?
大きな和太鼓の演奏を聴くと、耳にも聴こえますが、身体が何かに殴られたようにズシンと響きますよね。これって、太鼓に張っている皮を叩くと、皮が震えて周りの空気に振動を与えます。震えた空気の振動が、遠くで聴く我々に届きます。太鼓に限らず、楽器はそれぞれ何らかの方法で空気を震わせているのです。
あ、我々がおしゃべりする声も同じでした。口からだけでなく、喉、胸からの声は出ている(響いている)のです。
ライブでは音のシャワーを浴びるなんて言葉もありますが、本当に音の振動を浴びていることになります。
エンジニアさんは、各楽器の音、メインボーカルがきちんと聴こえるようにと、聴いてくれるお客さんの環境や機材を考えながらミキシング作業、いわゆる調整をしているのです。
ただ、あまりにもヘッドホン(イヤホン)用に向けて仕上げるとそれはそれで、大きなスピーカーで聞くとアンバランスになるので、色々バランス取りをして決めていくようなのです。
エンジニアさんの耳は、わたしには聞こえない音も聞こえるようです。
また、ボーカルのピッチなども、本当に微妙なミスも分かるようです。
これって「プロの領域」と言う奴だと思うのです。
演出家、作画さんたちが、ラッシュチェック(動画映像のチェック)していると、とある1コマが見えていてリテークを発見しますので、それと同じなんだと思うばかりでした。
また色指定さんは、一瞬の色間違いを発見します。
それぞれのプロが、一般人の我々には、聞こえない音、見えない絵、肌で感じる、匂いや五感で感じることがあると言うのは、この頃からより深く考えました。
わたしは、この「プロの領域」が、サイバーフォーミュラで言うところの「ZEROの領域」だと勝手に考えていました。
時代劇で、武士や忍者が「殺気」を感じて闘うのを見ても、これも、「ZEROの領域」だなって思っていたのは内緒です。
寿司職人が、何度握っても握るシャリの米の数が同じになると言うテレビを見たことがあって、凄いなと思ったのですが、これもわたしには「プロの領域」=「ZEROの領域」だと思うのです。
決して超能力ではなく、研ぎ澄まされた感覚がそれぞれ宿っていると思うのです。
プロは、経験によって裏打ちされる多い情報量とそのなかのどれを使うか?などの処理能力が素早く、的確なのだと思うのです。
わたしは、そんな理解をして「サイバーフォーミュラSAGA」を作っていました。
ハヤト、加賀たちプロのレーサーたちがしのぎを削るレースの物語ですが、我々作り手側にもそれぞれのドラマがあるなってニヤニヤすることもありました。
BGMのエンジニアさんに至っては、楽器数が幾つもあっても、それらの音場を作り出します。「SAGA」は30以上の楽器があります。「SIN」は、50以上の楽器がありましたね。
わたしたちが、コンサート風景で良く見るのは大ホールのステージに演奏家が楽器を持ってずらっと並んで演奏しているシーンだと思います。
しかし、BGMなどの収録は、楽器ごとに区切られたブースに入っていることが多いです。
いわゆる、楽器ごとに別トラックに収録するのです。
つまり、エンジニアさんが、自分の耳で聴いて、まるで大ホールのステージに楽器を並んでいるような感じに調整をします。
楽器の位置、広さや楽器の音量などが細かく調整して、音場が作られていくのです。
と言うことで、今後サントラ(BGM)を聴くときに、それぞれの楽器がどこに置かれていて、どれくらいの広がりがあって、音量はどうなのか?など、こんな聴き方もしてみてください、とても面白いですよ。
エンジニアさんや音楽プロデューサー、ディレクターの考えでそれぞれ違っております故に!!
この後、シングルCD、サントラCDともに、マスタリング作業にも立ち会いました。
これは、CDにするためのマスター作りです。このマスターをCD工場に持っていって、発売用のCDが生産されるのです。
歌の順番、歌と歌の間(ブランク)をどれくらいのタイムにするのか?など決めていきます。
チャプターとも言いますね。
あと、それぞれの詩、曲の音量も調整していきます。このマスタリング作業で決めたことが発売するCDになるので、慎重かつ丁寧に作業が続きます。
藤田さんは、音楽関係の色々な過程を見せてくれました。
ど新人プロデューサーのわたしにとって、とても有意義であり、実になる仕事だらけでした。
余談ですが、収録、ミキシング作業等々、古里にとっては待ち時間が多くなります。
そこで、藤田さんに色々レクチャーを受けていました。さらに、藤田さんが頼むお弁当が楽しみでした。「今日は、お肉、お魚、中華、ピザ、どれにしますか?」などのセリフが飛び交います。色々な料理店のメニュー表が並びます。エンジニアの助手さんが、各人のオーダーをメモに書いて、出前してくれるお店に電話をするのです。
同じ釜の飯を食う、と言うことわざがありますが、当時少しばかりですが音楽関係者と同じ釜の飯を食った記憶がありまして、あのときに出会った方々、元気かな?いまどうしているかな?と遠い目をしてしまいます。
業界が違いますので、本当に一期一会になってしまうことが多いのです。
この原稿を書きながら、ちょっと郷愁にひたっています。
次回は、音で声優さんたちとの出会いを書きたいと思います。
追伸:
YOUTUBE「ふるさとPアニメ道」もスタートしましたので、ぜひぜひチャンネル登録の上、ご覧くださいませ。
🔻リンクはこちら
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UC_JRVVLJSFUHGMXPCVYUQ5A
🔻ふるさとP写真録:今週の一枚

古里尚丈(ふるさとなおたけ)
1961年5月3日生まれ。青森県出身。
1982年日本アニメーションに制作進行として入社。1985年スタジオ・ジブリ『天空の城ラピュタ』制作進行。1987年サンライズ入社『ミスター味っ子』『勇者シリーズ』等、制作進行・設定制作・制作デスク・APを務め『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』からプロデューサー就任。『星方武俠アウトロースター』『GEAR戦士電童』『出撃!マシンロボレスキュー』『舞-HiME』『舞-乙HiME』他、オリジナルアニメーションを14作企画制作。
2011年2月企画会社、株式会社おっどあいくりえいてぃぶを設立。『ファイ・ブレイン~神のパズル』や『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』で企画・プロデューサー。『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』企画協力、『グレンダイザーU』アソシエイトプロデューサーとして参加。現在、ゲーム等参加、新企画を準備中。


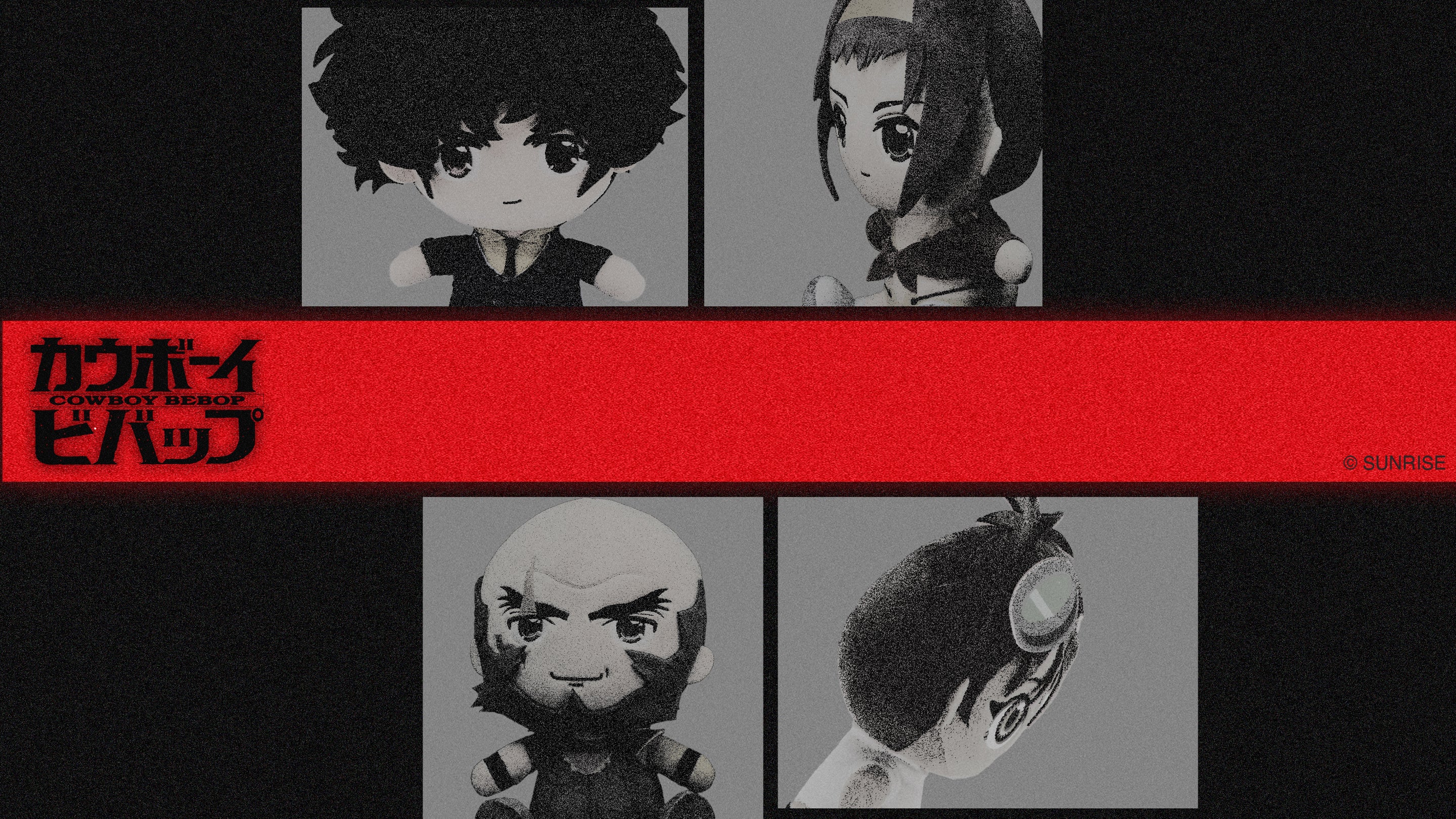


コメントを書く
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。