第10話:『音響仕事、アフレコの次はダビングです』
音響作業。
アフレコの次は、ダビングとなります。
これは、収録した声(セリフ)、音楽(BGM)、効果音(SE)を合わせる作業となります。
さらに、ダビング作業を行うには、フィルム(映像)の状態を少しでもカラーにしなければなりません。もし、出来ないとしても原画や動画にして絵を埋めていかなといけません。
つまり、絵がないと音を付けることが出来ないことになります。
「SAGA」のアフレコ時は、原画撮影やラフ原撮影が多く、色付きの撮影は少ないのです。
ですから、ダビングスケジュールに焦点を絞って色を付けることを頑張ります。
でも、なかなか簡単に進まないのが制作現場です。
カラーに出来なかったカットに必要な効果音があるとしたら、その音を入れてもらう箇所に記しを付けたりします。ラッシュと呼ばれるフィルムに、例えば、足音だとしたらタイムシートを見て、歩いて地面に足が着地するタイミングを直接マジックやデルマ(ダーマトグラフ)などで記し「(×)バツ」を書き入れる場合が多いです。
ちなみに、皆さん「デルマ」を知っているのでしょうか?
芯の出し方が少し特殊なので記憶に残っています。くるくるとりんごの皮を剥くように幅の狭い紙?を螺旋上に引っ張るのです。学生時代も使った記憶があります。
カラーになればこのような作業をする必要はないのですが、でも、作画の遅れ、セルのペイントの遅れ、背景の遅れなど色々な状況が重なってしまい、カラー化出来ないのです。その代わりに効果のスタッフさんに分かるように色々指示書を作成したりします。
でも、カラーにならないと、例えば地面が土なのか?コンクリートなのか?木材なのか?が分かりません。そうなると効果さんは、足音を入れるときに悩むことになります。
室内も同様で、壁がどんな材料で作られているのか?広さなどが分かると、音の響きなどが変わります。
事実、相手の立場になってみると見えることがたくさんあります。
さすがに、効果さんにはなれない自分ですが、ダビングに参加することで少しずつ意味、理由を知ることが多く、本当に悩んだ時期でもありました。
思い起こすと、わたしが日本アニメーションで制作していたときも、線撮りでした。
ジブリ時代も同様で、カラーと線撮りが混じっていました。
そして、サンライズでも同じなのです。
時代が変わっても、この状況が大きく変わっていないのは、本当に辛いです。
さて、ダビング当日、参加メンバーとして、福田監督、音響監督の藤野さん、音楽プロデューサーの藤田さん、各話の演出家さん、バップの田村プロデューサー、わたしとなります。
そして、効果音担当はフィズサウンドクリエイションの蔭山(満)さんです。
専門用語として、効果のスタッフのことを「効果マン」と言います。
ここでまた名刺交換です。
わたしは、蔭山さんと仕事をやるのは初めてなのです。勇者シリーズは効果音の会社は同じでも担当スタッフが違っておりましたので、会えなかったのです。
正直、オールカラーに出来なかったので、ビクビクしながらの名刺交換でした。
蔭山さんは、……笑顔……でした。
わたしは、オールカラーに出来なかったので、この笑顔の裏側では怒っているのでは?と勝手に妄想していましたが、淡々と作業は進んでいきます。
当時、蔭山さんは「蔭やん」と呼ばれていました。
蔭やんとたわいのない話、お馬鹿な話が出来るようになるには、ここから数年後になります。
福田監督の意見、音響監督の藤野さんの意見などに対応して、別な効果音に変更したり、音量を大きくしたり、音楽を変えたり、音楽の出だしなどの位置を変えたり、ステレオなので左右の音場の調整をしたりします。
このシーンは曲を聴かせたいので、効果音をなしにしたりもします。
あるいは、このシーンは、声を聴かせたいので、効果音も曲もなしにすることもあります。
合わせて、セリフも、間などを鑑み、絵の口パクとは関係なく前後に位置を変更したりします。この場合は、カットを再撮して口パクをずらします。
蔭山さんは、TVシリーズから参加している効果さんですので、「サイバーフォーミュラ」に必要な音源をたくさん持っているのです。
今なら、デジタル作業になり、ハードディスクに音源がたくさん入っていることになりますが、当時は、まだデジタル作業ではありませんでした。
つまり、アナログ環境での作業なのです。
監督と音響監督から急遽オーダーで新しいが効果音が欲しいとなると、蔭山さんがバイクに乗ってご自身の会社に戻って音を取ってきたと言う記憶があります。
あと、その場で効果音を作ってマイクで録音することもありました。
これは、CDドラマのダビング時だった記憶があります。
蔭山さんの戻りまで、待ちのタイミングになったかなと思います。
あと、サイバーフォーミュラSAGAのCDドラマもたくさん作りました。
CDドラマのアフレコも本編同様普通にやります。CDドラマはOVA本編と違って基本コメディ要素が強くなるので、アフレコも笑いの多い時間になります。
アフレコを終えて、後日ダビングになりますが、こちらには絵は必要ありませんのでドキドキせずに立ち会えます。
ですが、福田さんは「CDドラマのダビングは古里さんに任せた!」と言って参加しないのです。
「え? あ、はい」
やはり、わたしはドキドキせざるを得ません。
わたしは、勇者シリーズではCDドラマの音響作業に参加したことがないのです。
だから、ダビングの立ち会いに役に立たない可能性大なので、それでも、よろしいのでしょうか?状態です。
福田さんとしては、藤野さんがいて、蔭山さんがいるわけだから問題ないでしょう、状態なのです。
確かに、そうです。
わたしは、ダビング完了したら最終確認として聞いてOKを出せば良い役割なのです。
正直、一回目のダビング参加はただいるだけ、二回目は少し意見を言ってみたり、三回目は、効果音の変更や音量などに意見やアイデアも言えるようになり徐々に慣れていきます。
わたしのやるべきポイントも分かってきました。
プロデューサーとしてやるべきポイント、聴くべきポイントは、単純に言い間違いがないか、使ってはいけない言葉ではないか?ですが、これはアフレコ時に気づけ!ですよね。
あと、雑音など素人が聴いて分かるミスを指摘する、と言う感じでしょうか?
いわゆる、わたしが素人ですから、わたしが気づくことは直せよ、と言うことですよね。
ちなみに、とあるシーンに付ける音楽を別な曲に変えてもらいたいと言うのは本来監督の仕事なのですが、気になるときわたしからもお願いしました。
でも、自信はないので内心ドキドキなのです!
そう言えば、CDドラマ用に作曲家の佐橋さんに特別にBGMを作ってもらった記憶があります。
その理由として、SAGA本編の曲は使用するシーンに合わせて作っていますし、ドラマちっくな曲が多いのでCDドラマには使いづらいのです。
正直CDドラマに欲しいBGMはライトでコミカルな曲なのです。
でも、それらが少ないのです。と言うことで、コミカルでライトな曲やドタバタ系の曲。気持ちサスペンス系の曲などシンセサイザーで数曲作ってもらうことになりました。
なんと、わたしは、佐橋家に伺って佐橋さんの持つパソコンとシンセサイザーで作曲、キーボードを弾いて楽器も音色もその場で作った曲を聴く役割でした。
あっと言う間に、シンセサイザーで、セレクトした楽器もピアノと弦などシンプルなかたちで、曲自体は繰り返しの多い盛り上げのないものをパパっと作り終えてしまいました。
わたしはその1時間か2時間の間、佐橋さんのとなりで、「ハアー!凄い!何で作れるの?」状態です。
口あんぐりですよ!
アニメの場合、シナリオや絵を見ると動きや芝居が想像できるのですが、音楽は、五線譜のオタマジャクシを見てもどんな曲になるのか?がわかりませんので、とにかく頭のなかで音楽が鳴らないのです。でも、佐橋さんはあっという間に生み出すことができるので、わかっていてもビックリなのです。
音響監督、効果マン、調整のプロたち。作曲家の佐橋さんと、それぞれのプロの仕事、それこそ「プロの領域」を近くに感じる日々でした。
CDドラマのダビング作業が夕方から始まることが多かった記憶があります。
数時間後音響チームの見事な連携プレーで終わりが見えてきます。
でも、すでに真夜中であり、わたしはソファで仮眠。本当に、皆さんお仕事しているのに、ひとり寝てしまいごめんなさい!!
朝、納品テープが出来まして、バップさんに納品となります。
現在のデジタル化、パソコンでの作業は、色々な音源をハードディスクに入っていますし、また、トラックも無数に増やすことが出来ます。
新しい音の追加なども、その場でハードディスクからコピーとなり、対応出来ます。
当時は、音をたくさん足していくことなどの作業が大変だったと思います。
2chのオープンテープやいくつかのトラックを持ったテープなどアナログでの機材があったかと思います。
当時、それらをどうやって使っていたのか?
作業工程を教えてもらっていなかったことを、いまさらに後悔しています。
今後、どこかで知ることが出来たら、書きたいと思います。
ちなみに、皆さんも昔のアニメを見るときに、「音」も気にして聴いてくださると面白いと思います。思ったより、効果音も少ないし、曲も少ないことがありますので……。逆に、いまは効果音の音数も多いし、曲もたくさん入っていたりします。
次回は、第1巻の発売、そして、晴海最後のコミケに参加したことなど書きます。
追伸:
YOUTUBE「ふるさとPアニメ道」もスタートしましたので、ぜひぜひチャンネル登録の上、ご覧くださいませ。
🔻リンクはこちら
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UC_JRVVLJSFUHGMXPCVYUQ5A
🔻ふるさとP写真録:今週の一枚

古里尚丈(ふるさとなおたけ)
1961年5月3日生まれ。青森県出身。
1982年日本アニメーションに制作進行として入社。1985年スタジオ・ジブリ『天空の城ラピュタ』制作進行。1987年サンライズ入社『ミスター味っ子』『勇者シリーズ』等、制作進行・設定制作・制作デスク・APを務め『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』からプロデューサー就任。『星方武俠アウトロースター』『GEAR戦士電童』『出撃!マシンロボレスキュー』『舞-HiME』『舞-乙HiME』他、オリジナルアニメーションを14作企画制作。
2011年2月企画会社、株式会社おっどあいくりえいてぃぶを設立。『ファイ・ブレイン~神のパズル』や『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』で企画・プロデューサー。『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』企画協力、『グレンダイザーU』アソシエイトプロデューサーとして参加。現在、ゲーム等参加、新企画を準備中。


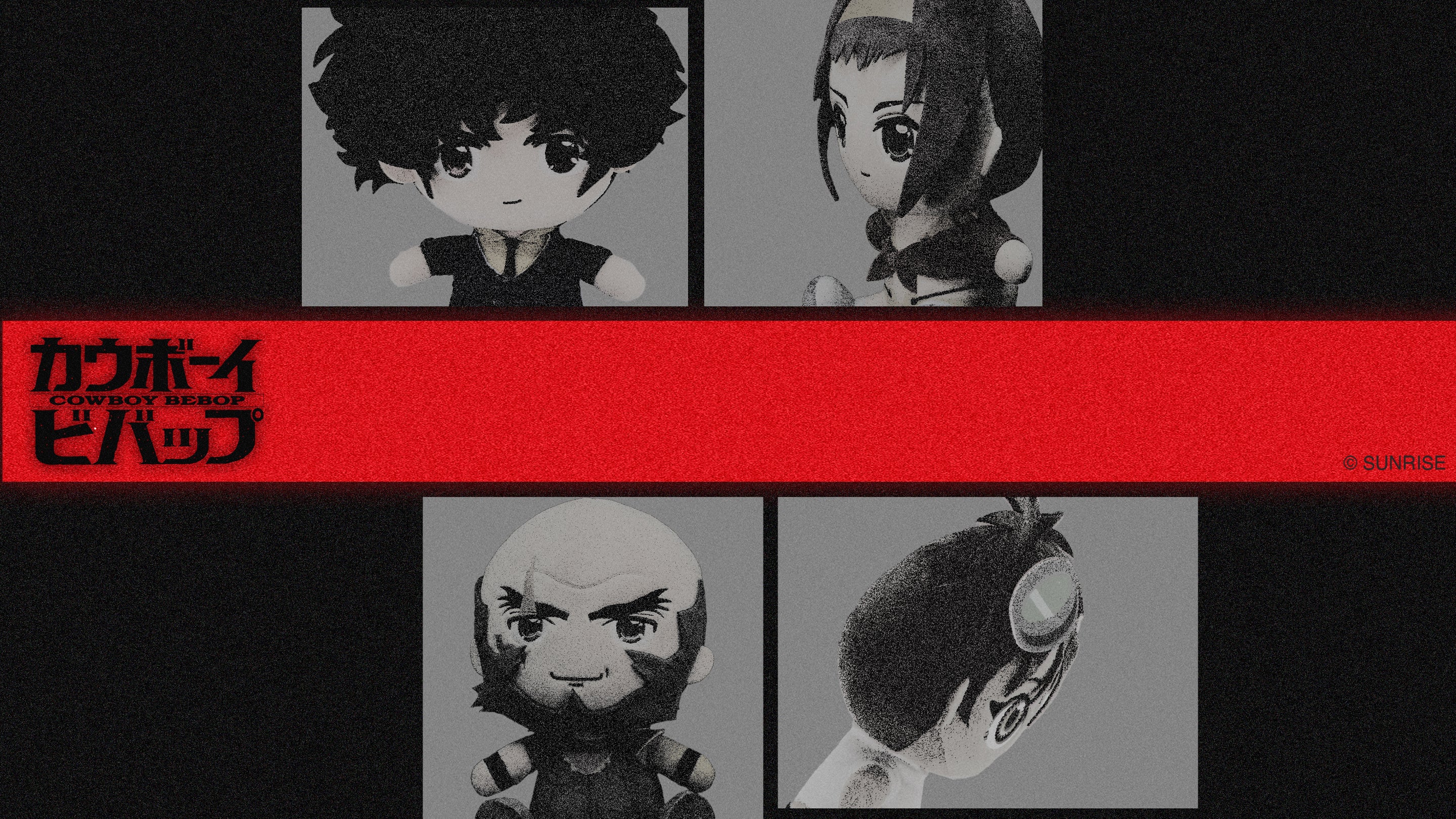


コメントを書く
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。