第24話:『アナログ時代のアニメは、人の持つ能力(ちから)が見えやすい気がするのです』
天空の城ラピュタのイントロのド頭のシーン、捉えられたシータを狙って飛んでくるドーラ一味から始まり、逃げるシータが飛行船から落ちていきメインタイトルが出ます。
「メインタイトル」が出たシーンの背景は「ハーモニー処理」となっています。
天空の城ラピュタのオープニング部分のハーモニー処理は、大昔石壁などに描かれた絵のようなディテールのテクニックなので厚塗りではありません。
あるいは羊皮に描かれた絵のようなニュアンスなのかな?と思います。
そして、本編に出てくるゴリアテや装甲列車などもハーモニー処理をしていますね。
浮島、天空の城などのカットは、大判の原画であり、止めのセル画をスライドさせて撮影しています。
ときおり、プロペラなど動いていますが、基本は止めなのです。
ちなみに、ハーモニー処理で有名なのは、出崎(統)監督の「あしたのジョー2」、劇場版「エースをねらえ!」「宝島」などでキャラクターの映えタイミングをストップモーションとして魅せる絵作りです。
そこで、その止め絵は単なるセル画塗りではなく背景(美術)さんにレタッチをしてもらうのです。
ラピュタでは、ハーモニー専門のスタッフさんがおりました。
日本アニメーションでも、サンライズでも美術のスタッフさんが担当していますね。
だからこそノーマル、影のセル塗りで終わらず、背景的なディテールが描き込まれ重厚になります。
ちなみに現代はこのテクニックを使う作品は少ないですね。
多分、デジタル作業とはこのテクニックは相性が悪いのかしら?
ラピュタのオープニングシーンのハーモニー処理は、240フレームの大判原画をセルにトレースしなくてはいけません。
※フレームとは、レイアウト各サイズのことを言います。通常を100フレームと言って、それより小さいと80フレームとか、大きいと120フレームとか、そして、240フレームが一番大きいフレームになります。当時のカメラ台の関係で、このサイズの撮影が限界なのです。
そして、大判セルのトレースをやれる機械は都内に数台しかありません。
その機械。仕組みと言うか、構造はほぼコピー機なのです。ただし、紙にコピーではなく透明なセルにコピーをするといったことになります。
特殊な機械の1台は東映アニメーションにあるので電話連絡してスケジュール予約をして伺うことになります。
わたしがほぼ担当?と言うくらい東映アニメーションに行きましたね(笑)。
だんだん顔なじみになっていきました。
東映アニメーションは、当時のジブリの社長の古巣でもあり、また、宮崎監督の古巣でもありますので、わたしが電話しても色々優遇してくれました。
この大判作画は仕上げ、レタッチ作業も大変ですが、撮影がより大変です。特に、一部プロペラが回っているカットがありますが、これはプロペラは動画になっており数枚を置き換えて撮影します。そう、デカいセルを都度置き換えるのはとても手間がかかります。
止め絵になる下絵があり、その上にプロペラのセルを置いて、さらに、その上に大きなガラスが圧着します。そして、カメラのシャッターを押すわけです。
そうしたら、まずガラスを外し、セルを外してまた別のセルを乗せ換えて、ガラスを圧着してシャッターを押すの繰り返し。
さらに、カメラワークとしてトラックバックやトラックアップ、PANなどあるとそのセルを少しずつ動かしてシャッターを押す作業が加わります。
アナログ時代の撮影は気の遠くなるような手作業でアニメーションが生まれていました。
映像を見るとあっという間に過ぎ去るようなシーン、カットでももの凄い手間がかかっている場合があり、それが、垣間見れると別な感動が押し寄せてきます。
いまでも、思い出すこととして、金田(伊功)さんが描いたドーラの子分たちと町のおじさんたちの殴り合いのモブシーンは必見です。端っこにいるおじさんやおばさんがそれぞれ演技をします。みんなが同じ動きではないのです。それぞれのおじさんたちがニヤリと笑ってみたり、来るかいと煽ってみたり、やれやれだなって余裕をかましてみたり、します。奥さんたちもそれぞれ自分の旦那さんを応援したりと様々です。
さらにさらにドーラの息子たちも良い味を出します。
また列車とドーラの車が走るなか線路が崩れていくシーン、ラピュタ島の財宝を盗むセコい軍人たちのモブシーン。これらは、一枚の絵のなかに何十人ものキャラクターが、描かれており別々にアクションをしています。宝物を個性豊かに持っていきます。
ラストシーンあたりの鍋の底が割れてキューブが崩れ落ちていくカットも細かい動きとなっていますね。スケジュール的にも終わり際に上がった原画だったので動画スケジュールが少なかったので何人かで分けてやった記憶がありますね。
記憶のなか、1カットの動画が1ヶ月かかることはざらにありました。
わたしたち進行は、進捗状況を確認するためにずっと描いている動画マンに都度聞きにいきます。1週間、2週間、3週間……、やっと目処がたってきて、「あと、2日で終わると思う」と言われると、本当に嬉しい気持ちになりました。
これは、そのカットが終わると言う気持ちだけでなく、やっと、その担当動画マンが、そのカットから開放されるのがわたしたちも嬉しいからなのです。
でも、そんなモブシーンのカットも誰かがやらないと終わりませんので、また、頼むのですが、何だか心が痛む自分がいました。
さて、モブシーンはアニメ映画の醍醐味です。
CGなどがなかった時代。
全て手描きのあの時代。
原画の上がり。
動画の上がり。
仕上げの上がり。
紙に描かれた背景上がりを束でもらう醍醐味。
これら、それぞれをリアルに見ることの出来る制作進行はそれこそお宝を常に見ている状態でした。
都度それかのカットを見るなりに、「はあースゲー!」。
人の持つ能力(ちから)を再認識するのでした。
ちなみに、いまのデジタルも加味した時代、確かにアナログ時代より簡単になったり、早くなったり、楽になった部分はあります。
さらに、デジタルだからこそやれる出来ることを踏まえて、より発展して欲しいと願っています。わたしは、パソコンもインターネットもタブレットも道具なので、紙から変わっただけで結局はそれらを使う人の使い方次第で素晴らしきクリエイターの世界が開かれると考えています。
さらにさらに、オリジナリティ豊かな物語を生み出して作る、魅力的なキャラクターを生み出して動かすことは、クリエイターたちの頭のなかにあるものを引っ張り出してアニメにしていくことなので、それはいつになっても変わらぬ難しさや大変さがあるのだと思うのです。
わたし自身、色々思い出してブログを書いていますが、昔が良かったと思っているわけでもないです。いまは、いまの技術を用いて面白いアニメを作って欲しいですし、これらに携われる進行になった若者もいまの時代の醍醐味を見つけ出して楽しんでいって欲しいなと思うばかりです。
追伸
ちょうど「天空の城ラピュタ」を制作しているときに、日本アニメーションで名作アニメ「愛少女ポリアンナ物語」が放送(1986年)していました。
主人公ポリアンナが「良かった探し」をしているのを思い出します。
つらくても、何か、どこか、どれかに「良かった探し」をしている前向きな主人公です。
ネガティブなところが目について、どうしてもマイナス面を言うことがあります。そうではなく、「良かった探し」をして行きたいと、見習わなくてはいけないと自分に言い聞かせる、そんな時代でした。
🔻ふるさとP写真録:今週の一枚

追伸:
YOUTUBE「ふるさとPアニメ道」もスタートしましたので、ぜひぜひチャンネル登録の上、ご覧くださいませ。
🔻リンクはこちら
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UC_JRVVLJSFUHGMXPCVYUQ5A
古里尚丈(ふるさとなおたけ)
1961年5月3日生まれ。青森県出身。
1982年日本アニメーションに制作進行として入社。1985年スタジオ・ジブリ『天空の城ラピュタ』制作進行。1987年サンライズ入社『ミスター味っ子』『勇者シリーズ』等、制作進行・設定制作・制作デスク・APを務め『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』からプロデューサー就任。『星方武俠アウトロースター』『GEAR戦士電童』『出撃!マシンロボレスキュー』『舞-HiME』『舞-乙HiME』他、オリジナルアニメーションを14作企画制作。
2011年2月企画会社、株式会社おっどあいくりえいてぃぶを設立。『ファイ・ブレイン~神のパズル』や『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』で企画・プロデューサー。『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』企画協力、『グレンダイザーU』アソシエイトプロデューサーとして参加。現在、ゲーム等参加、新企画を準備中。


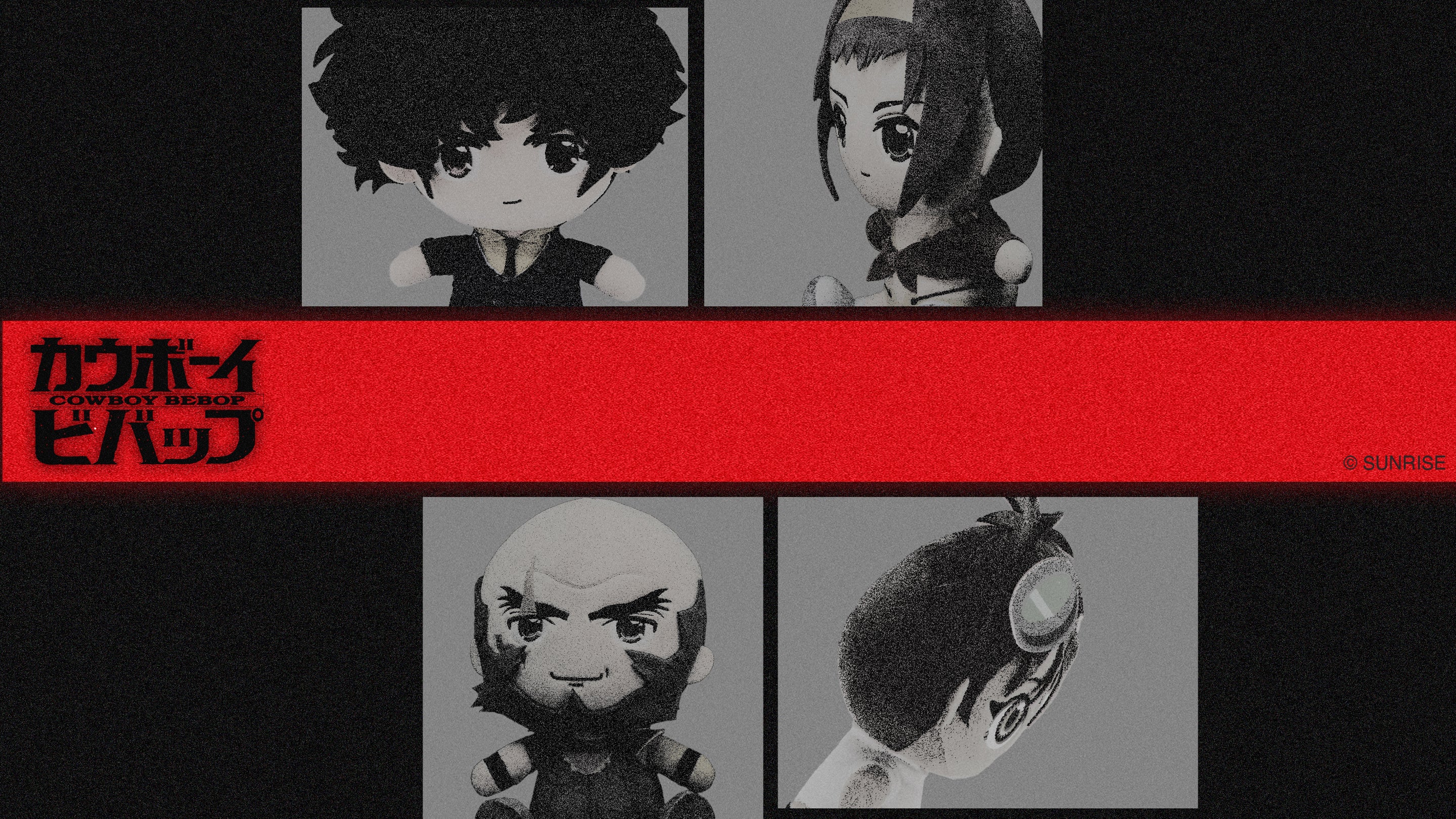


コメントを書く
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。