第56回:『勇者エクスカイザーは、母と子に贈るロボットバトル絵本!なのです』
「勇者エクスカイザー」、わたしの仕事はメカデザインの打ち合わせから始まりました。
と言っても、間髪入れずにキャラクターデザイン打ち合わせ、美術打ち合わせがやってきます。
当然、シリーズ構成打ち合わせからプロット、シナリオ会議もドンドン組んで行きます。
わたしは、これら打ち合わせスケジュールを組んで、兎に角前に進めます。
定例になる会議はスケジュールを定めて会議室を押さえます。
5名以上入れる会議室は、スタジオにはひとつだけなので、上井草駅前の本社の5階会議室を借りることになるのですが、本社にも大きな会議室はひとつしかないので、早いもの勝ちなのです。
と言うことで、当時のスタジオ風景を少しだけ書きます。
制作チームとして「ミスター味っ子」班は第7スタジオと呼ばれていました。
その班がそのまま「勇者エクスカイザー」班になりますので、第7スタジオ管轄です。
ビルの2階にあり1階はコンビニでした。
十字路の対面にデニーズがありました。
上井草駅まで徒歩で15分程度かかります。
第7スタジオは上井草駅前にある本社から見ると、けっこう遠い場所にあるスタジオとして認定されていました。
そして、スポンサーであるタカラのメンバー参加のメインメカデザイン会議は本社ビルの5階でやっていましたので、わたしは先に行って、お茶や資料など準備しておりました。
と、言うことで大河原(邦男)さんが描いた勇者ロボットのデザインは本社ビル3階のコピー機を借りて印刷していたのです。いつも使うので恐縮して借りていましたが、わたしとしてはやることがあります、必ずコピー機のガラスの盤面を拭いてからコピーをしていました。
理由は少しでも綺麗にコピーして関係者に渡したいからです。
あと、常にコピーの色具合やカスレ具合を見て、濃さなど調整していました。
たくさんコピーをしてるので、どうしても線が薄くなってしまうようで、仕方ありません。そして、一番の問題は、コピーが薄いなと思って濃くすると用紙全体がグレーになってしまうことでした。指紋なども写らないようにと気を使っていました。
なるべく、白い紙に綺麗な黒線でコピーしたいので、これは都度調整&挑戦でした。
ちなみに、良く壊れて他のスタジオにコピー機を借りてコピーしたこともあります。
設定制作のわたしが「勇者エクスカイザー」の仕事として重要かつ大切なメカデザインの次はキャラクターデザインについてです。
素敵なキャラクターを描いていたのは、キャラクターデザイン初挑戦の平岡(正幸)さんです。なんと、平岡さんは、わたしと同じ年齢でした。
オリジナルアニメのデザイナーとして、27~28歳で参加したのです。
若くして大役を担っているので、わたしは尊敬!でした。
わたしの第一印象は、華のある清潔なデザインを描くアニメーターさんだなと感じました。
少年漫画の方向でなく、ちょっと少女漫画のニュアンスの入った非常にクリーンな絵柄だと思った次第です。子供向け、特に幼児を含めての「エクスカイザー」には合ってると思いましたし、吉井(孝幸)プロデューサーのメッセージでもある「母と子に贈るロボットバトル絵本」のキャラデザインとして合っていると考えました。
平岡さんとわたしがゲストデザインを考えるとき、少女漫画のなかから、あれだよ!これだよ!と参考を考えたことは内緒です。
いま、思い出すのは、ゲストキャラクターでアイドルが出る話数がありました。
当時のアイドルの森高千里が良いかも?って話し合った記憶があります。
ちょうどデビューして20歳くらいの森高千里さんでした。
その森高千里さんがいまもステージに立っているのを見ると驚きます。さらに、いまも若いのでびっくりです。
「母と子に贈るロボットバトル絵本」のメッセージのなか「絵本」部分を考えると、背景(美術ボード)が絵本風味だったと思うのです。
美術監督は、メカマンの岡田(有章)さん。正式名、デザインオフィス・メカマンは、「機動戦士ガンダム」の美術監督の中村光毅さんの会社です。
岡田さんは、とてもSFに精通している方です。
でも、「勇者エクスカイザー」は、1990年あたりの世界観であり、現実に即した設定を描いてもらっていました。
視聴者である子供たちの知っている世界(環境)から大きく逸脱しないように手掛けていました。
さらにロボットが登場してもおかしくない世界観を目指していました。
だからこそ世界観はある意味リアルなんだけれど、アニメーションの背景はパステル調であり、少し可愛い感じになっていたと思います。
このバランスが、「母と子に贈るロボットバトル絵本」につながる部分であり、大きなファクターだったと思うのです。
岡田さんが描く背景ボードと、平岡さんが描くキャラクターが相まって、より絵本風味になるのですが、……、そこに福田(満男)さんの絵コンテ、作監チーフの服部(憲知)さん、オープニングなどの作画の大張(正己)さんのロボットの見せ方がめちゃくちゃ格好良いのです。このバランスが絶妙なアニメだと思うのです。
メインの勇者ロボットたちの変型合体、必殺技、オープニングの絵コンテ・演出は福田さんが担当しています。ちなみに、わたしが担当した「GEAR戦士電童」のオープニング映像と「勇者エクスカイザー」を見ると何かしらのつながりを感じますよ。
エクスカイザーの発進から変型は、アニメーターの山本(佐和子)さんが原画を描いています。
キングエクスカイザー、ドラゴンカイザー、グレートエクスカイザーの変型合体、オープニング作画は、アニメーター大張さんが描いていますね。
ゴッドマックスの変型合体は、アニメーター吉田(徹)さんが描きました。
ウルトラレイカーの変型合体は、アニメーター奥野(浩行)さんが描いていると思います。
キングエクスカイザー、ドラゴンカイザー、グレートエクスカイザーの必殺技、いくつかのメカ作監等、作監チーフの服部さんが担当しています。
服部さんには、設定なども描いてもらっています。
これら変型合体、必殺技のカットをまとめたフィルムのことを「DN」と専門用語で言います。
子供たちが何度も観ることに耐えられるような絵作りをするのです。本編にはない影、ハイライトもあって動きもスムーズで丁寧に描いています。透過光のエフェクトもたくさんあって派手で格好良いアクションとなり、通常のテレビシリーズではやらない絵作りになります。
本編カットのフィルムに、この変型合体などの「DN」のフィルムを編集で入れ込むのです。
この「DN」の作り方などの説明は後日に書きますね。
ここが、「母と子に贈るロボットバトル絵本」のコンセプトのなか「ロボットバトル」の部分に当たるかも知れません。
さらに、いまだから言えますが、下記コンセプトがありました。
「将を射んと欲すれば先ず馬を射よ」と言うことです。
「勇者エクスカイザー」の場合、将とは「子供たち」です。
「馬」は両親、祖父、祖母です。
つまり、子供たちにアプローチするのではなく、親、祖父祖母にアプローチせよ!なのです。
スポンサーであるメーカー側からすると、子供たちに玩具を買ってもらうには、親が子供のために買ってやろうとなるように宣伝、告知をしなくてはなりません。
子供たちしか知らないアニメのロボットの玩具を欲しいと言っても、お母さんにとっては「何それ?」になります。
でも、母と子が一緒に「勇者エクスカイザー」をテレビで観て物語を楽しみ、お母さんが自発的にエクスカイザーの玩具を子供に買ってやろうと考えるような、そんなアニメを作りたい!のです。
だから、「母と子に贈るロボットバトル絵本」なのです。
お母さんからすると、ロボットバトル物は、愛しい息子が戦いを好むようになるのでは?とか、危ないことをやるかもと母目線でネガティブに考えるかも知れません。
でも、「勇者エクスカイザー」は、母と子が一緒に観て、物語も丁寧に作っているし、優しさを感じてもらえる絵本風味なので、このアニメは観てOK、玩具も買ってOKだと思ってもらえるようになると嬉しいなと考えて制作していました。
わたしは、玩具発売後、とあるデパートの玩具売り場から少し離れたところから子供たちの行動を見ていたこともあります。いま考えると、けっこうヤバい兄ちゃんですね。
正直、ハラハラ・ドキドキ、子供がエクスカイザーたちを手に取ると、「良し、ありがとう」と心のなかで叫び、一喜一憂するのです。
さらに「買ってください!」と願い、手に汗握るわけなのですが、……お父さんは買ってくれませんでした。
本当にガッカリしたわたしは、まだまだ知られていないんだなって思うわけです。
もっともっと頑張って面白いアニメを作るぞ!と心に誓う、そんな20代後半の自分でした。

古里尚丈(ふるさとなおたけ)
1961年5月3日生まれ。青森県出身。
1982年日本アニメーションに制作進行として入社。1985年スタジオ・ジブリ『天空の城ラピュタ』制作進行。1987年サンライズ入社『ミスター味っ子』『勇者シリーズ』等、制作進行・設定制作・制作デスク・APを務め『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』からプロデューサー就任。『星方武俠アウトロースター』『GEAR戦士電童』『出撃!マシンロボレスキュー』『舞-HiME』『舞-乙HiME』他、オリジナルアニメーションを14作企画制作。
2011年2月企画会社、株式会社おっどあいくりえいてぃぶを設立。『ファイ・ブレイン~神のパズル』や『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』で企画・プロデューサー。『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』企画協力、『グレンダイザーU』制作統括として参加。現在、ゲーム等参加、新企画を準備中。


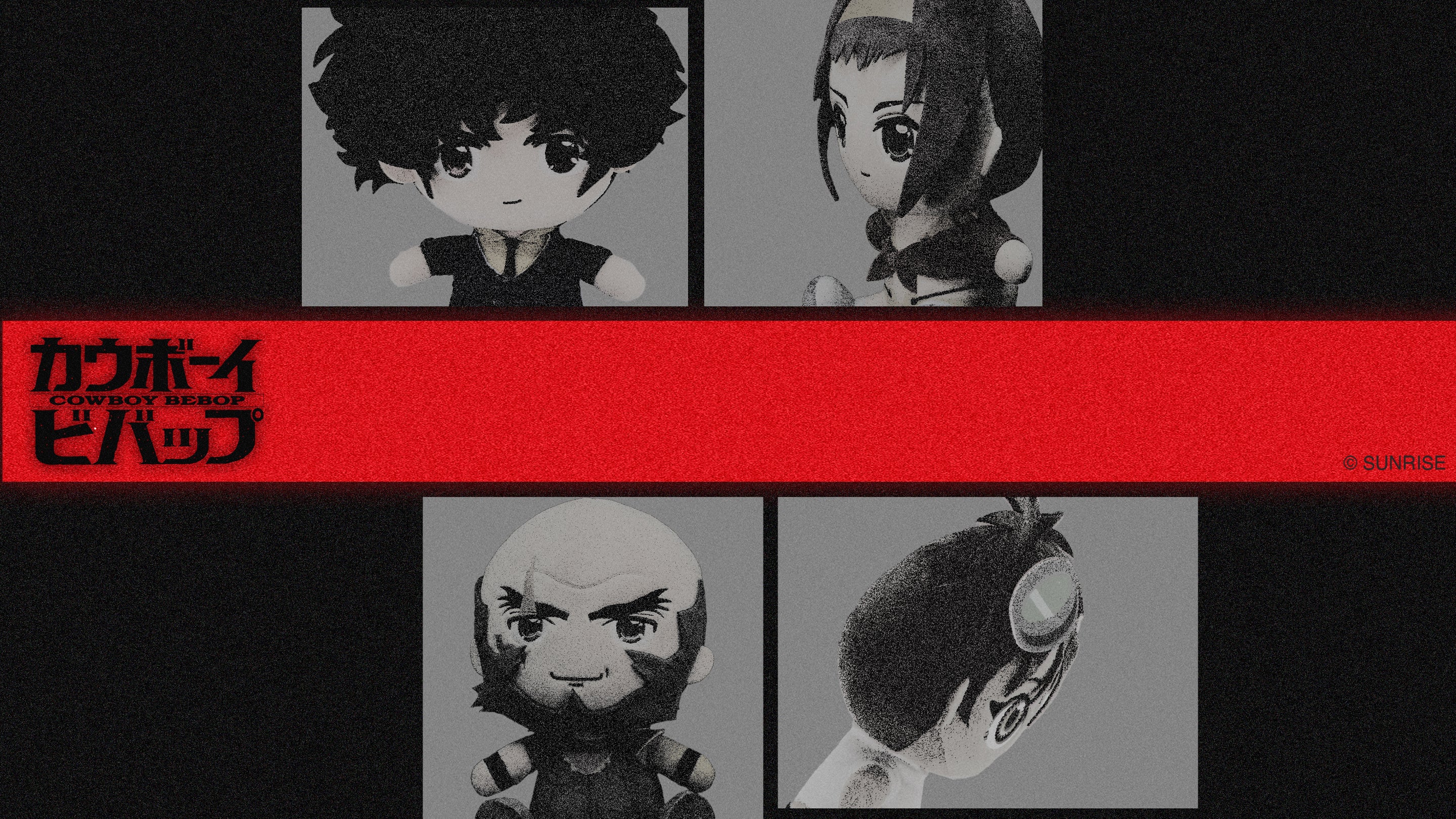


コメントを書く
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。