第61回:『太陽の勇者ファイバード、シリーズ2作目の面白さと辛さと制作デスク!?』
勇者シリーズ2作目が「太陽の勇者ファイバード」になります。
放送は、1991年2月2日から全48話でした。
となると、企画そのものは「勇者エクスカイザー」の放送約1年前から動くことになります。
「勇者エクスカイザー」の放送が1990年2月3日ですが、放送とほぼ同じ頃に「勇者シリーズ第2作目」のメインロボットのデザインや新企画案が動き出します。
メインスタッフとして、吉井(孝幸)プロデューサーを中心に、谷田部(勝義)監督、シリーズ構成の平野(靖士)さん、メカデザインの大河原(邦男)さんは前作と同じです。
まず、「勇者シリーズ第1作目」の主人公ロボットが車だったので、「2作目」はジェット機が主人公ロボットになりました。そうなると、「勇者シリーズ第2作目」新企画として、大きなファクターとなるロボット設定が決まりました。
つまり、玩具メーカーのタカラさんが出してきた新しいロボットのモチーフが決め手になります。
それに、アンドロイドが加わりました。
なんと人間サイズのヒーローも出すことになりました。
さらに、秘密基地を出すことになりました。
「勇者エクスカイザー」は、町と一戸建ての家のガレージに車(エクスカイザー)がいましたので、第2作目では基地に各ロボットたちがいることになるのです。
「勇者エクスカイザー」とは、色んな面で変化しています。
幾つか書いてみます。
主人公ロボットは、車からアンドロイド&ジェット機に。
拠点は、お家から基地に。
行動範囲は、ご町内から世界に。
主人公も人間サイズで敵も人間サイズ。
大人の代表として、両親から博士に。
基地があるので、各機発進シークエンスも生まれました。
いきなりですが、わたしはウルトラセブンに出てくるウルトラホークの発進が好きです。
また、サンダーバードの発進も子供の頃、ワクワクしながら見ていました。
スポンサーであるタカラさんの商品である男児玩具のターゲットは変わっていません。
玩具もデザインの変更はあっても、コンセプトに変更はないのです。
つまり、乗り物形態から人型ロボットに変型・合体!これは変わりません。
売り物が大きく変わらないことになるので、どうしても、物語やそのための世界観などアニメの見た目を変えたくなるのだ、と、思うのです。
この残すべきところは残して、変えるべきところは変えることになりましたが……。
ターゲットである子供たちがワクワク出来る物語でないと駄目です。
でも、子供たちに分かる物語でないと駄目です。
正直、第2作目はSF色が強くなり、バトル色も少しだけリアリティが増した気がしました。
「親と子に贈るロボットバトル絵本」のコンセプトを持つ「勇者エクスカイザー」から、「絵本」のニュアンスが少し減ったなと思いました。
わたしは、設定制作として、作業を行うなか心の奥で何かしら分からないのですが、寂しさを感じたのも事実です。
と言うことで、シリーズ化2作目の各設定を作ったり、プロットを書いてもらったりするのですが、1作目と2作目の違い、つまりその「塩梅」が難しいなと思ったのです。
この時に経験したこと考えたことがから、わたしは「舞-HiME」の後の「舞-乙HiME」を作るときの2作目の変え方の参考になっています。
当然「太陽の勇者ファイバード」は、作っていて楽しかったし、火鳥兄ちゃんが愛嬌あって、浮世離れしていて少しばかりトンチンカンな行動をするのは面白かったなって思います。
わたしは、監督、プロデューサー、そして各スタッフが、「主人公キャラを愛せる?」と言うことがとっても大切で重要なことだと思うのです。
火鳥兄ちゃんは、間違いなく愛されキャラでした!!
勇者シリーズ第2作目として「勇者エクスカイザー」と色々な面で変わることが重視されていたように思い出します。
当時、それらの変化ってどうして起きているのか?を考えました。
そう言えば、大先輩たちが作った「ウルトラマン」の次が「ウルトラセブン」だったな?と思ったのです。
怪獣から宇宙人に、ドラマも少し大人っぽくなり、やはりSF色が強くなると言う流れは、何かしら似ていると感じました。
仮面ライダーシリーズを見ても似たようなことを感じますし、共通した何かがあるのだろうと思います。
あの時期、色々考える癖がついた気がします。
「何故なのか?」
「どうしてなのか?」
と、スタート地点を知り、ゴールも知ることで、その間の経緯も踏まえて、勇者シリーズの
3~4作はオリジナルアニメの作り方、考えたをより知る時期だったと、いまさらに思います。
つまり、わたしは、勇者シリーズを経験していないと、これら諸々に到達するには長い時間がかかったのではないかと思うし、もしかすると辿り着けないままの人間だったのかも知れないと思ったりします。
「太陽の勇者ファイバード」の動き出しは、わたしは「勇者エクスカイザー」も動いていましたので、設定制作として参加し、色々業務を行っていました。
そんな中「勇者エクスカイザー」の中盤頃、吉井プロデューサーから呼び出しがありました。
会議室で開口一番。
「古里くん、将来何をやりたいのか?」
これは、わたしの将来像を聞いているのです。
一瞬フリーズしましたが、わたしの頭の中では、ひとつの答えがありました。
「プロデューサーをやりたいです」
吉井プロデューサーは、「分かった。それでは、企画書を書いて来い」と。
それから、内容、スケジュールなど指示されました。
次の日、わたしは、電気屋さんにワープロを買いに行ったのです。
※第23話の原稿にこのネタを少しだけ書いています。
企画書を一生懸命に書いて、2週間後に吉井さんに渡した記憶があります。
ちなみにその企画書は、オリジナルのロボットアニメです。
実は、コピーは残しておりますので、事務所のどこかにあります。
数日後、吉井さんから「次の勇者シリーズは、古里が制作デスクをやれ」と。
当時「勇者エクスカイザー」は最後まで設定制作です。
そして、「太陽の勇者ファイバード」は制作デスクなのです。
でも、動き出しのタイミングでは、設定制作も兼ねてやっていました。
サンライズに入社時の最初の面接も吉井さんです。
そして、「新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA」でプロデューサーになった時も、吉井さんに呼び出されたことから始まりました。
わたしの人生で、分岐点に常にいるのが吉井さんなのです。
ちなみに、「舞-HiME」の企画の動き出しや、起業を考えた時に灯台のように行くべき方向を指してくださったのは、内田(健二)社長(2011年当時)です。
上司の吉井さんと内田さんのおふたりが大きな目標でもあり、素晴らしき大先輩です。
出会えたことに大感謝です。
あと、どうしてわたしがプロデューサーをやりたいと答えたか?と言いますと、当時わたしは設定制作の仕事が本当に大好きでした。
向いていると心の底から思っていました。
それこそ、一生設定制作をやりたいと思ったのも事実です。
でも、そんなことは無理です。
そこで設定制作に一番近い役職が何なのか?を考えました。
そして、出した答えは、「監督」か「プロデューサー」になることだと思ったのです。
企画やデザインにOKを出せるポジションはこの両者です。
よって、「プロデューサー」になる!をゴールにしました。

古里尚丈(ふるさとなおたけ)
1961年5月3日生まれ。青森県出身。
1982年日本アニメーションに制作進行として入社。1985年スタジオ・ジブリ『天空の城ラピュタ』制作進行。1987年サンライズ入社『ミスター味っ子』『勇者シリーズ』等、制作進行・設定制作・制作デスク・APを務め『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』からプロデューサー就任。『星方武俠アウトロースター』『GEAR戦士電童』『出撃!マシンロボレスキュー』『舞-HiME』『舞-乙HiME』他、オリジナルアニメーションを14作企画制作。
2011年2月企画会社、株式会社おっどあいくりえいてぃぶを設立。『ファイ・ブレイン~神のパズル』や『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』で企画・プロデューサー。『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』企画協力、『グレンダイザーU』制作統括として参加。現在、ゲーム等参加、新企画を準備中。


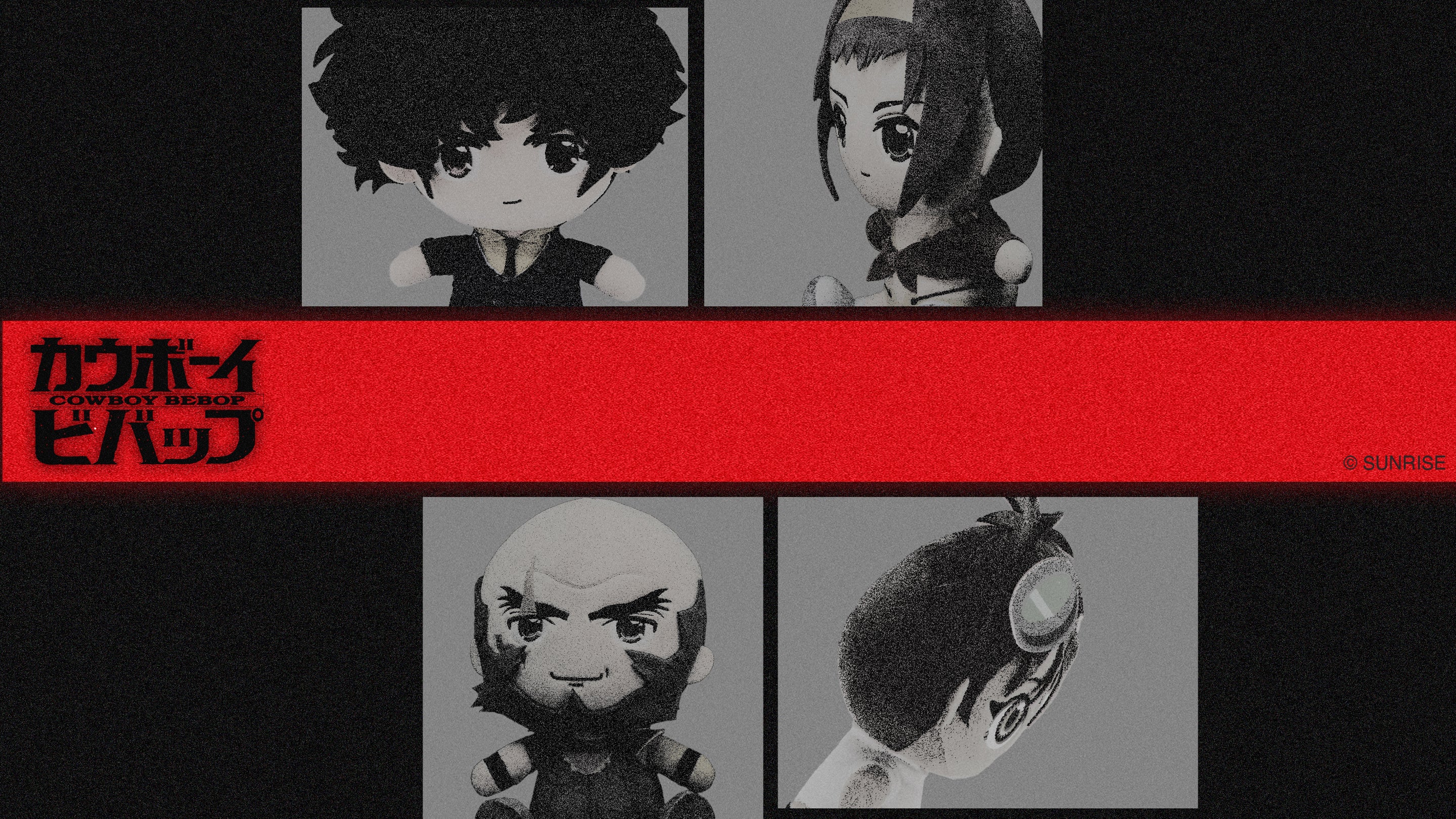


コメントを書く
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。