第65回:『太陽の勇者ファイバード、アナログ時代フィルムと初号のお話』
「太陽の勇者ファイバード」を作っていたあの時代。
現在と違ってフィルムで撮影し、現像所でフィルムを現像しての流れで、最終的に「プリント」を焼いて放送局に納品していました。
さて「フィルム」とは、何か?
当時、写真撮影に使用していたのはフィルムでした。それは、透明なフィルムのベースに「ゼラチン」と呼ばれる、銀塩を含む感光乳剤が塗布されています。
レンズを通った光を受けてカメラ内部にある感光乳剤を塗布したフィルムに感光し化学変化を起こします。その化学変化で生まれた細かい粒子群が光を透過させたり、通さなかったりして陰影が生まれるのです。
アニメの撮影はネガフィルム(陰画)を用いて撮影します。
ネガには映る被写体の色味が白が黒に黒が白に、赤が緑にと反転するのです。
そのネガからポジ(陽画)フィルムを作ります。
そのポジはわたしたちが見ている世界、いわゆる正しい色となります。つまり、ネガフィルムがあれば何本でもコピーしたかたちでポジフィルムが作れるのです。
と、言うようにフィルムにはネガフィルムとポジフィルムと言う2種類があります。
※2023年放送「魔法の天使クリーミィマミ」に出てくる猫のキャラ名が「ネガ」と「ポジ」と言いますね。
昔の写真は、ネガフィルムから印画紙に焼き付けをして化学変化が起きることでわたしたちの見ている世界が紙の上に固定されます。
プロカメラマンは、ポジフィルム(リバーサルフィルム)を使っていることが多いのです。それは、色味が忠実に出るのでポスターなどに使うことが多いです。
現在、フィルムから印画紙への焼き付けから大きく変わったのが、デジタルカメラで撮影したデータをパソコンなどを用いてプリンターでの印刷となりますね。
わたしは、中学、高校時代に写真部。そして、写真学校に通っていたりもします。
ですから、カメラ、撮影からフィルム現像、引き伸ばし機で印画紙に焼き付けなどやれます。
アニメーションの制作マンになっても撮影・フィルム現像などの内容を理解出来ました。
当時、撮影フィルムには16ミリと35ミリと言うサイズがありました。テレビシリーズは16ミリサイズの使用が多かったです。これは、コストを下げることが出来るからです。理由は、16ミリのフィルムは面積が小さく、お値段が少し安くなるのです。
ただし、35ミリフィルムは映画館の上映に使うサイズなので画質が良く綺麗です。
と言うことで、勇者エクスカイザーも太陽の勇者ファイバードも16ミリのフィルムを使用しておりました。
ちなみに、16ミリより小さいサイズの家庭用8ミリフィルムもありました。
・フィルム名:16ミリ
・サイズ:10×14mm
・フィルム幅:16mm
・フィルム名:35ミリ
・サイズ:24×36mm
・フィルム幅:35mm
あと、アニメの撮影用のフィルムメーカーは、「富士フィルム」と「コダック(EK)」の2社でした。
実は、メーカーによって色合いが違うのです。また、フィルムには感度と言うものがあります。その感度の違いでも色合いが変わるのです。だから、作品のセル画の色合いによって、どの色味を綺麗に表現したいのか?でフィルムの持つ個性を踏まえて決めるのです。あと、カメラとレンズによっても色味が変わるので、キャラクターのセル画の色味を見るためにテスト撮影を作品ごとに行っていました。
ちなみに、「GEAR戦士電童」は富士の35ミリサイズで感度200のフィルムを使った記憶があります。子供向けのアニメなので赤、青など綺麗に発色するフィルムを使いました。
そして、わたしが時折「DN」と言ってしまう専門用語があります。
ロボットたちの変形、合体、必殺技、発進など、色々な話数で使う動画があります。これは、ネガをたくさん作る必用があるのですが、昔はネガから直接ネガを作ることが可能でしたが、勇者エクスカイザーの時期くらいから、ネガからポジを作って、そこから改めてネガを作ることになりました。
これを「デュープネガ(DN)」と言います。「デュープ」の日本語の意味は「撮影した写真フィルムを複製すること、また複製されたフィルムのことを言います。
と言うことで、わたしたちは「DNカット」と呼んだりしました。あるいは、「DNシーン」とも言いました。
デジタル時代、ビデオ時代のいまは、データコピーは楽ちんな作業ですが、フィルム時代はとても大変でした。あと、アナログコピーなので画質が悪くなるのです。
フィルムにはネガとポジがあると書きましたが、通常局納品はポジフィルムです。
それを「プリント」と言います。
いわゆる、言葉としては「プリント納品」となります。
勇者シリーズは、納品前に東京現像所で最終チェックを行います。
それを、「初号試写」と言います。
東京現像所は、調布は深大寺の近くにあります。
2023年11月30日をもって事業が終わっています。時代の流れではありますが、とても悲しいです。当時のスタッフさんの顔が思い浮かびます。
サンライズは上井草にありますので、そこから調布の東京現像所まで車でフィルムを運んで現像しラッシュを回収と、日々行くことが日課でもありました。
ですから、近道の開発、進行たちが競争をして、今日は何分で着いたなど言い合っていました。
ちなみに、わたしは一番早くて25分でした。他の進行は20分で着いたなど自慢していました。とにかく、事故のないように運転して欲しいものです。
初号は、メインスタッフを乗せて行きます。10名以上で行くので車を3台出します。当然安全運転で行くのですが、近道を使うと酔うからと嫌がられて不平不満が出ることもありました。狭い道路で畑の横など道路がガタガタなので車が揺れるんです。
車は無事に到着し、わたしたちは真っ暗な試写室でスクリーンに映る映像を見てリテークは残っていないか?と、最終チェックです。
スタッフみんなが目を皿のようにして見ます。
これは、緊張しますね。
つまり、アニメを楽しめることは出来ません。
でも、それでもやはり楽しいシーンは楽しいし、悲しいシーンは悲しい。
感動シーンは素直に感動しますよ。
わたしは、チェックなのでドキドキしつつも、楽しんでいたような気がします。
初号試写は東京現像所のなかの小さい映画館のような試写室をつかいます。
100人分の座席はなかったと思いますが、でもたくさんの人が観ることの出来る大きなスクリーンがありました。
多分、150~200インチくらいだったのかな?と思います。
初号は、毎週毎週あります。
それこそ初号がないと言うことは、納品が遅れることになりますので緊張します。
大きなスクリーンだからこそ、みつかるリテークも、あります。
なぜ、スタジオで何度も何度も見てるのに気が付かなかったんだ!と言うことがありました。
リテークがたくさんあるカットは、一度に全てのリテークを直せず、ひとつ直して撮影してフィルム現像をして「ラッシュフィルム」を見ます。
ちなみに、この「ラッシュ」と言う専門用語は、撮影が終わってチェックするために用意するポジフィルムのことです。
映写機で見るためにはポジであるラッシュフィルムが必用なのです。
当然、音もありませんし、カットもバラバラで本編のようにつながってもいません。
この「ラッシュフィルム」は映画業界の専門用語ですね。
当時のアニメ業界でも使っていました。
いまだと、何と言うのか?です。単に「カットを見ます」なのかしら?
でも、「第〇話のラッシュチェックします」といまでも言うのかな?
若い知り合いのプロデューサーに聞いてみようと思います。
とにかく、リテークが直ると次のリテークかみつかのは仕方がないことかも知れません。どうしても、注視して見るとそこばかりを見て、アチラコチラを見ていないんですよね。
自分では広く見ているつもりでも、1点を見ているんですね。
人間の目は、不思議ですよね。
かなり広く見て、でも、集中するとある1点を見ることも出来る。でも、ズームレンズのように望遠として見たい部分に寄る訳ではないんです。また、両目で見ているからこそ、立体として見ることが出来ます。片目を瞑って見ると立体感がなくなり、歩いてて段差などに躓いてしまいますよね。
さらに、聴くこと、人間の耳はマイクのように全ての音を拾う訳でなく聴きたい音だけを聴き分けるんですよね。
例えば、喫茶店でザワザワしたなかで大好きな人の声を聴くぞ!と集中するとザワザワが減り、何とか聴こえてきます。
カメラもマイクも機械は優秀ですが、人間は脳で判断して見たいもの、聴きたいことを手に入れるんです。これは、すごいことだなと常に思います。
改めて、初号ですがあの頃の音声は、モノラルでした。
いまは、ほぼステレオですね。
さて、このモノラル音声がプリントにきちんと焼き付けられており、映写すると絵に合わせて音が出ます。
音について、「音ネガ」と言うフィルムもありました。
音響さんが作った音を音ネガに焼き込み、現像して絵と合わせて現像してプリントを作るんです。
アナログ時代の技術は、知ると楽しいです。デジタルより理屈が分かりやすいのです。
もしかすると目に見える部分が多いからなのかも知れません。
初号で大きなスクリーンでスタッフたちと見ると、「終わった!」と言うピリオドが打てたこと、達成感を都度味わうことが出来たことも良かったです。
そして、初号の行き帰りに車を出すのですが、そのなかの1台はわたしが運転手になることが多いです。
わたしの車には、演出家さんや作画監督さんなど、たまに、局のプロデューサーなどが乗ることが多いです。
助手席に乗った演出家さんと東京現像所に行き、また帰る時間は合わせると約1時間あるので、色々お話が出来たのがとても楽しかったし、とにかくゆるい話が出来たことが互いの距離感を縮めることが出来たのではないか?と思います。
とある演出家さんと帰りに、わたしが「今日の話数、良かった!面白かった」と言ったことがあります。素直な感想を話したのです。
そうするとその演出家さんは、「感想を言ってくれる制作さんはいないから、古里くんありがとう」と話してくださいました。
さらに「古里くん、珍しいね」と褒められたのかな???です。
でも、その演出家さんに言われたことから、自分の意見を素直に口にする意味があるんだなって思いました。
そうです。きちんと言葉にしてお話しないと相手には伝わらないです。
当然ですが、こちらの思いを相手に話す、伝えることの大切さを感じました。
初号は、わたしにとってひとつのコミュニケーションの場にもなっていたのかも知れません。

古里尚丈(ふるさとなおたけ)
1961年5月3日生まれ。青森県出身。
1982年日本アニメーションに制作進行として入社。1985年スタジオ・ジブリ『天空の城ラピュタ』制作進行。1987年サンライズ入社『ミスター味っ子』『勇者シリーズ』等、制作進行・設定制作・制作デスク・APを務め『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』からプロデューサー就任。『星方武俠アウトロースター』『GEAR戦士電童』『出撃!マシンロボレスキュー』『舞-HiME』『舞-乙HiME』他、オリジナルアニメーションを14作企画制作。
2011年2月企画会社、株式会社おっどあいくりえいてぃぶを設立。『ファイ・ブレイン~神のパズル』や『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』で企画・プロデューサー。『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』企画協力、『グレンダイザーU』制作統括として参加。現在、ゲーム等参加、新企画を準備中。


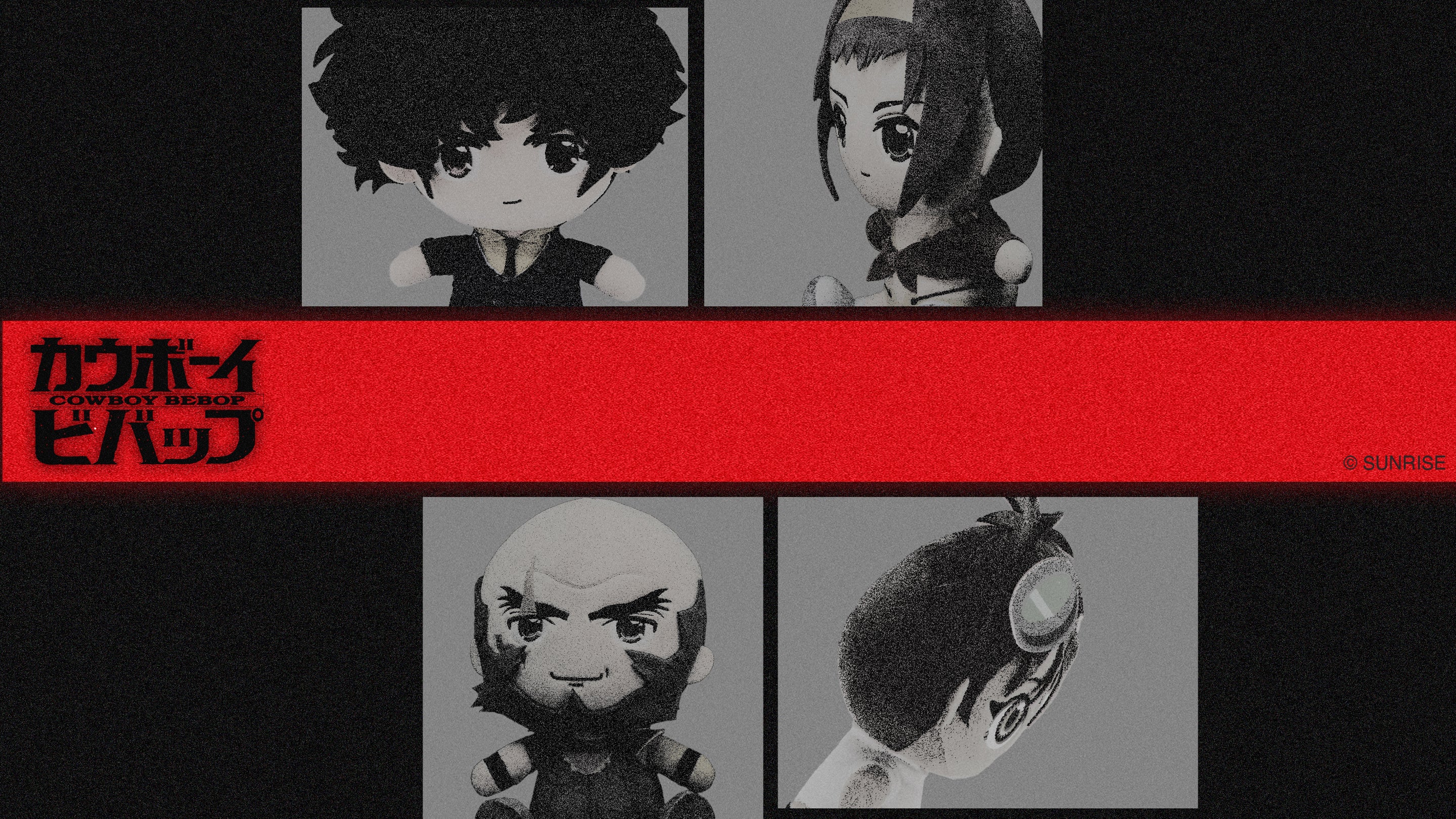


コメントを書く
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。