第67回:『舞-乙HiME、キャラクタースターシステムって何だろう?』
「舞-HiME」から「舞-乙HiME」の企画時に、コンセプトとして「キャラクター・スターシステム」と言うキャッチコピーを作りました。
では、この「キャラクター・スターシステム」とは、何か?を説明します。
まずは、「スターシステム」について書きます。
もともとはハリウッド映画で使われていた言葉です。
スター俳優を企画の中心に据えた映画作りを目指し、そのことを称して「スターシステム」と呼びました。
それ以来、スターを中心とした映画製作システムのことを呼び習わすようになりました。
手塚漫画における「スターシステム」とは?
漫画の神様、手塚治虫氏における「スターシステム」は、上記ハリウッド映画の場合とは少し違います。
漫画の登場人物をさながら映画俳優のように扱う、のです。
つまりひとりの役者がいろいろな役を演じるように、ひとりのキャラクターがいろいろな役に扮してマンガを演じている、ということです。
宝塚歌劇における「スターシステム」とは?
宝塚歌劇の大きな特徴の一つでもあるスターシステムとは、トップスター候補を育成するためのシステムのことです。
人気・実力・スター性・容姿などを兼ね備え、作品の中で重要なポジションを担当する生徒のことを、「スター」と呼びます。
各組のスターの中で上位となる3番手、2番手、トップスターを頂点とした、ピラミッド型で構成されます。
また、お客様も、このスターが育つのをずっと追いかけることが楽しみになり、いわゆる推しキャラとして応援することになるのです。
これら「スターシステム」を活用しようと考えたのが、「舞-乙HiME」です。
そして、「舞-乙HiME」では、造語になりますが、売りの「キャラクター」と「スターシステム」を足したかたちで「キャラクター・スターシステム」と謳いました。
しかし、ある意味の実験は、わたしが担当したTVアニメ「GEAR戦士電童」のなかに出てきた3人のアイドルグループ「C-DRiVE」の少女たちを「舞-HiME」に起用したのが始まりとなります。ただし、「舞-HiME」では「スターシステム」とは謳いませんでした。
「GEAR戦士電童」のキャラクターデザインの久行(宏和)さんの魅力的なデザインを踏まえて企画したのが「舞-HiME」です。
その次作として企画したのが「舞-乙HiME」となります。
「舞-HiME」に出演したキャラクターを、別な役として新しい物語「舞-乙HiME」に参加してもらう企画です。
これは、ハリウッドの映画のそれと近いですし、また、手塚治虫氏の漫画のなかに出る「ロック」や「ランプ」「ヒゲオヤジ」と近いものだと考えています。
さらに物語の見せ方のヒントになった宝塚歌劇です。
宝塚の「スターシステム」は、トップ・スターを育成するものです。
宝塚には、生徒が400人くらいいます、そのなかで、たった5人だけがトップ・スターになれます。
スターになるために、何年も切磋琢磨します。
常に競争にさらされています。
そして、序列が生まれます。
その序列に応じて、配役の良さや出番の数、舞台での立ち位置など、その待遇はわかりやすくもあり、同時にシビアです。
わたしが、初めて観た宝塚の舞台「薔薇の封印」で、すぐに5番手くらいまでわかりました。
宝塚の「スターシステム」は当事者(タカラジェンヌ)にとっては大変ハードな仕組みだと思います。
しかし、わたしたち観客にとってのメリットがあります。
それは「わかりやすさ」です。
誰が主演で、誰が準主演なのか明確になっていることで、舞台の演目が格段に理解しやすくなります
明確な序列は、観客へのわかりやすさの提供なのです。
ファンにとっての「スターシステム」のさらなるメリットは、未来のトップ・スターが見えてくることです。
この「わかりやすさ」は、「舞-乙HiME」のキャラクターと物語の骨子にもなっています。
田舎から出てきたアリカが艱難辛苦のなか目標のオトメになる物語です。物語のなかでは、オトメになれずに田舎に帰る少女もいます。夢の実現には、残酷な現実が常にあります。
「舞-乙HiME」の世界観はファンタジーですが、物語はリアルに作っています。
これは、わたしたちが大人になると会社に入社し、仕事をして偉くなる人もいれば、夢を追って転職をしたりたどりつく人もいます。わたしのようにアニメ業界に入り、制作進行から、設定制作、制作デスク、アシスタントプロデューサー、プロデューサーになる人生も同じだと思うのです。
新人が数年かけて役をもらい、セリフをもらい、主人公を勝ち取る人生も同じだと思うのです。
ある意味、勝ち抜きはどんな業界にもあるし、常にわたしたちはその渦中にいるのではないか?と思ったのです。
わたしは、「キャラクター・スターシステム」を使って、「舞-HiME」から「舞-乙HiME」、そして、小説展開の「舞-HiME DESTINY(ディステニー)龍の巫女」「舞-HiME狂走曲(ラプソディ)猫姫@日記」があります。龍の巫女はCDドラマも作りました。ちなみに、主人公の真夜は「舞-乙HiME~0.sifl」に出演しています。
新作TVシリーズとして、新しい主役を迎えて「舞-HiME◯◯◯(仮)」の新作アニメを作りたかったな!と言う夢がありましたが、実現出来ず、サンライズを辞めることになりました。
残念です。

古里尚丈(ふるさとなおたけ)
1961年5月3日生まれ。青森県出身。
1982年日本アニメーションに制作進行として入社。1985年スタジオ・ジブリ『天空の城ラピュタ』制作進行。1987年サンライズ入社『ミスター味っ子』『勇者シリーズ』等、制作進行・設定制作・制作デスク・APを務め『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』からプロデューサー就任。『星方武俠アウトロースター』『GEAR戦士電童』『出撃!マシンロボレスキュー』『舞-HiME』『舞-乙HiME』他、オリジナルアニメーションを14作企画制作。
2011年2月企画会社、株式会社おっどあいくりえいてぃぶを設立。『ファイ・ブレイン~神のパズル』や『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』で企画・プロデューサー。『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』企画協力、『グレンダイザーU』制作統括として参加。現在、ゲーム等参加、新企画を準備中。


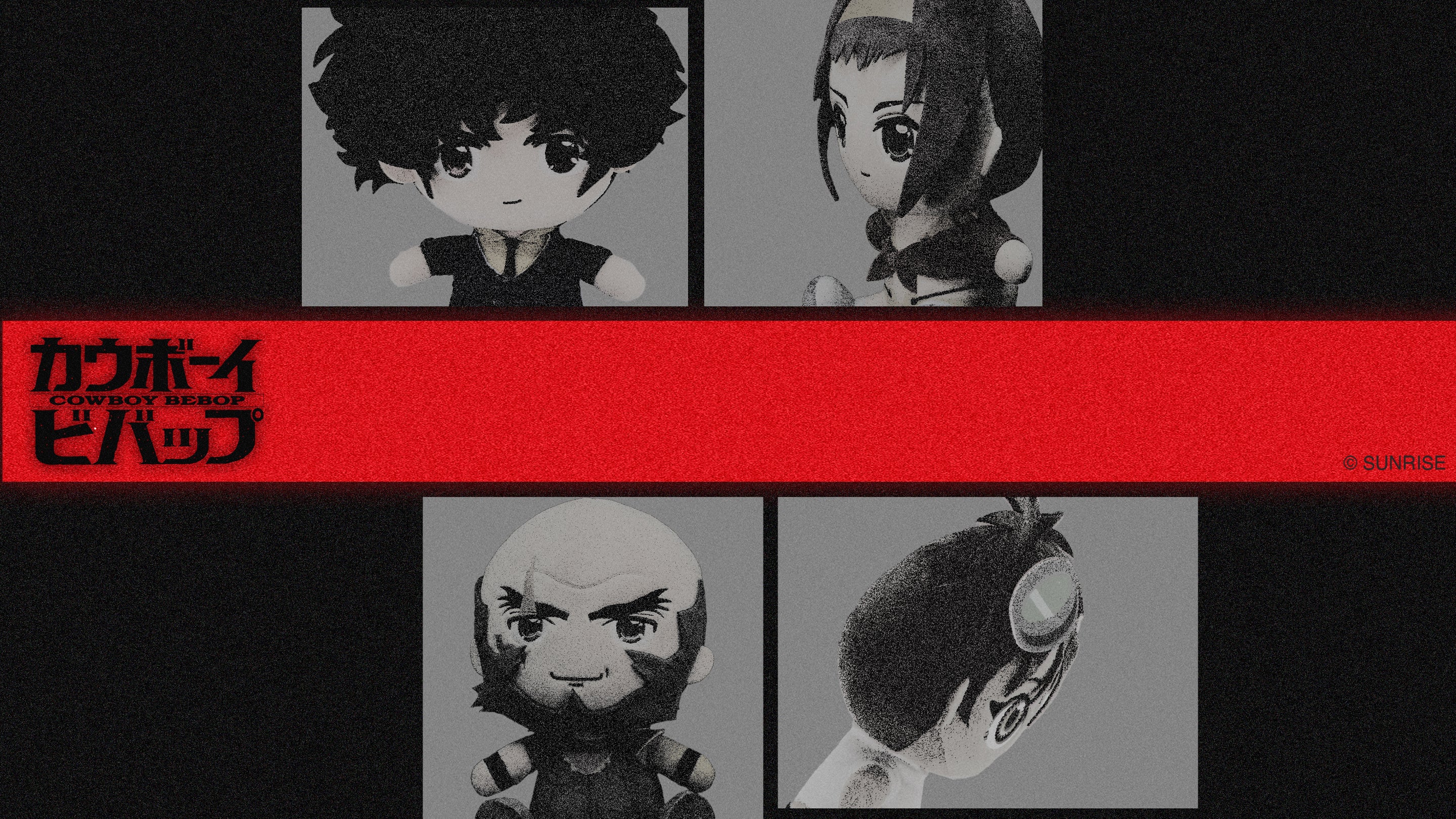


コメントを書く
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。